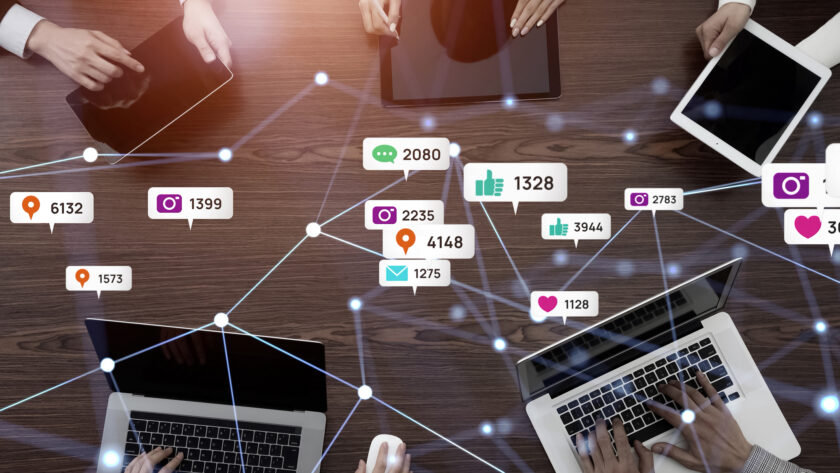
こんにちは、SNS分析ツール「クイッドモニター」のメディア運営チームです。
SNSマーケティングを進める上で、自社だけでなく他人のXアカウントを分析することは欠かせません。競合企業の取り組みや、成果を上げているアカウントの投稿傾向を把握することで、自社の改善点や成功のヒントを得られるでしょう。
特にフォロワー数の推移や投稿への反応を観察することは、ブランド分析や広告効果の評価に直結するはずです。
一方で、X公式のアナリティクスは自分のアカウント専用の機能に限られ、他人のアカウントの詳細なデータは確認できません。
そのため他人アカウントを客観的に調査するには、外部の分析ツールを活用する必要があります。
本記事では他人アカウントの分析方法や利用できるツール、注意点まで体系的に紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
なお、Xは以前「Twitter」という名称で広く利用されていましたが、2023年に「X」へと名称変更が行われました。
本記事では、名称統一のため「X」と表記して解説します。
目次

Xにおける他人のアカウント分析とは?
Xにおける他人のアカウント分析は、自分以外のアカウントを対象にしてその活動内容やフォロワーの動向を把握することを指します。企業やブランドが競合他社のアカウントを分析することで、マーケティング戦略の改善につながったり、消費者の関心や反応の傾向をつかめたりするでしょう。
例えば新製品のキャンペーンを行った際に、競合がどのような投稿をしているのかを観察すれば、自社の施策と比較しながら効果的な手法を導き出せる可能性があります。
またインフルエンサーの発信内容やフォロワーとの関係性を調べることで、どのテーマが支持を集めているかを見極められるはずです。
他人アカウント分析は単なる情報収集ではなく、自社のブランド強化や市場理解を進めるための実践的な手段といえるでしょう。
なぜ他人アカウントを分析する必要があるのか
他人アカウントを分析する理由の一つには、競合他社や業界の成功事例を把握すると、客観的な視点で自社の運用改善に役立てられることが挙げられます。競合がどのようなテーマで発信しているか、どの投稿がフォロワーから高い反応を得ているかを理解できると、より効果的な運用方針を打ち立てられるでしょう。
特に新規フォロワーの獲得やエンゲージメント率の向上を目指す際には、競合調査が重要な手掛かりとなります。
さらには、インフルエンサーの分析も重要です。
成功しているインフルエンサーの投稿パターンを調べれば、どのようなテーマやフォーマットが支持を集めているかを学べます。
具体的には、動画を主体にした発信が強いのか、テキスト中心でも一定の影響力を持っているのかといった点を見極められるはずです。
また他人アカウントのフォロワー層やエンゲージメント率を比較することで、自社アカウントがどの層に響いていないのかを客観的に把握することも可能です。
例えば同業他社のアカウントは若年層の支持が厚いのに対し、自社は中高年層に偏っている場合、そのギャップを埋めるための戦略を検討できます。
このように、他人アカウント分析は競争環境を俯瞰し、自社の方向性を定める上で欠かせないアプローチなのです。
他人アカウント分析で確認すべき主な項目
他人アカウントの分析では、いくつかの基本項目を押さえることが大切です。数値や傾向を丁寧に確認することで、相手の強みや課題を客観的に把握できます。
まず確認したいのがフォロワー数の推移です。
単にフォロワーの総数を見るだけでは不十分で、増減のタイミングに注目する必要があります。
短期間で大きく増えている場合は、キャンペーンや話題性のある施策が成功した可能性があります。
逆に減少が続く場合には、発信内容に改善の余地があるかもしれません。
次に重要なのが投稿へのエンゲージメントです。
「いいね」「リポスト」「コメント」などの反応を分析すると、フォロワーがどの投稿に強く関心を示しているかが分かります。
人気の高い投稿の傾向をつかめば、自社の投稿改善にも役立ちます。
また投稿の時間帯や曜日の傾向も欠かせない視点です。
同じ内容のコンテンツでも、反応率は発信のタイミングによって大きく変わります。
フォロワーがアクティブな時間帯を意識することは、効率的な運用につながります。
さらには、フォロワー属性や関心領域を把握することも有効です。
年齢層や居住地域、興味のある分野を理解できれば、自社が狙いたいターゲットとの一致度を確認できます。
もしギャップがあるようなら、その差を埋める施策を考えるヒントになります。
これらの項目を組み合わせて分析することで、他人アカウントの特徴を多面的に捉えられます。
得られた示唆を自社の運用に取り入れれば、より成果につながる改善となるでしょう。
X公式アナリティクスでできること・できないこと
X公式アナリティクスは、自分のアカウントの運用状況を数値で確認できる無料の分析機能です。投稿ごとのインプレッション数やエンゲージメント率、リンクのクリック数などを確認できるため、どの投稿が効果的だったのかを把握するのに役立ちます。
またフォロワーの属性として、地域や興味関心の傾向も確認でき、コンテンツがどの層にリーチしているのかを知ることが可能です。
ただし、この機能で確認できるのはあくまで自分のアカウントに限られます。
競合企業やインフルエンサーなど、他人アカウントのフォロワー推移や投稿傾向を直接調べることはできません。
そのため、競合調査や市場動向の分析といった目的で利用するには不十分です。
もし他人アカウントの情報を把握したい場合は、外部の分析ツールを組み合わせて活用しなければなりません。
外部ツールを利用すれば、フォロワー数の推移や人気投稿の傾向、競合との比較など、より実践的なデータを収集できます。
公式アナリティクスで自社の現状を把握し、外部ツールで他人アカウントを補足的に調査するという組み合わせが効果的です。
※参考:Xビジネス.「アナリティクス」.
https://business.x.com/ja/advertising/analytics ,(参照2025-08-21).
高度な検索(検索コマンド)でできること・できないこと
Xには「高度な検索」という機能もあります。高度な検索では、検索コマンドを活用することで特定のアカウントやキーワードに関連する投稿を絞り込むことが可能です。
これにより、他人アカウントの投稿内容を効率的に調査し、反応の多いツイートやトレンドを把握できます。
分析できる主な内容は以下の通りです。
- 特定アカウントによるポストやリプライ
- 指定した期間の投稿履歴
- 特定のキーワードを含む投稿
一方でこの機能は、過去の内容やよく見られた反応を確認することはできても、他人アカウントのフォロワー数の推移や属性情報などの定量データまでは把握できません。
つまり、投稿傾向を観察する定性的な分析には役立ちますが、フォロワー動向やエンゲージメント率などの数値分析に用いるには、適していないと言えるでしょう。
まずは外部ツールを活用し、さらに多角的に分析したい際や、細かく調べたい際に使える手段として捉えることをおすすめします。
※参考:Xヘルプセンター.「高度な検索の使い方」.
https://help.x.com/ja/using-x/x-advanced-search,(参照2025-08-21).
他人アカウントを分析できる外部ツールの種類
先述の通り、他人アカウントを分析するには外部ツールの活用が欠かせません。逆を言えば、公式アナリティクスや高度な検索では取得できない情報も、外部ツールを使うと詳しく把握できる可能性があります。
フォロワー数の推移や投稿ごとの反応などを自動で収集できるものもあり、手作業で調べるよりも圧倒的に効率的です。
外部ツールには無料と有料のものが存在し、取得できるデータの範囲や精度に差があります。
企業や代理店として活用する場合は、より多機能な有料ツールを採用すると良いでしょう。
他人アカウントを分析できる外部ツールは大きく3つに分けられます。
以下でそれぞれ詳しくご紹介します。
他人アカウントのフォロワー推移を分析できるツール
フォロワー数の推移を確認できるツールは、アカウント運用の成果を測定する上で非常に有用です。こういったツールでは、フォロワー数が増減したタイミングをグラフで表示でき、どの施策がフォロワー獲得に結び付いたのかを客観的に確認できます。
例えばキャンペーンを実施した週にフォロワーが急増していれば、その施策が効果的だったと判断できます。
逆に特定の投稿以降フォロワーが減少している場合は、発信内容やトーンに改善点があるかもしれません。
こうしたデータの活用によって、次の施策の方向性を明確にできるのがメリットです。
企業にとっては、自社のフォロワー数の変化と競合アカウントの推移を比較することで、市場の自社への関心度合いを知る手掛かりにもなります。
フォロワー推移を可視化できるツールは、日々の運用効果を評価し戦略を修正する際に欠かせない存在といえるでしょう。
他人アカウントの投稿内容・口コミ分析ツール
投稿ごとの反応を詳しく調べたい場合には、投稿内容や口コミの分析に特化したツールが役立ちます。こうしたツールによるデータを利用すると、単に反応の良い投稿を特定するだけでなく、人気のジャンルや効果的な表現方法を導き出すことが可能です。
例えば、短文の投稿が効果的なのか、画像や動画を含めた投稿の方が反応が良いのかといった違いを把握できます。
企業にとっては、広告キャンペーンや情報発信の内容を改善する指標になるでしょう。
日々の投稿データを積み重ねて分析することで、伸びやすいテーマや時間帯を特定でき、より戦略的なアカウント運用へとつなげられます。
トレンドや人気の投稿を分析できるツール
アカウント単位の分析の他、X全体で話題になっているトレンドや他人が挙げた人気の投稿を把握できるツールも存在します。こういったツールを活用すると、ユーザーの関心が集まるテーマや盛り上がりのタイミングを捉えることが可能です。
トレンドや人気投稿の分析は、単に流行を追いかけられるだけでなく、より多くのユーザーに自社の発信内容を届けるための工夫につながります。
特に競合との差別化やキャンペーンの方向性を決める上で、このような情報は重要な判断材料となるでしょう。
他人アカウント分析を行うときの注意点
他人アカウントを分析する際には、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。まず大前提として、Xの規約を遵守し、不正な手段でデータを取得しないことです。
非公開アカウントへのアクセスやツールを用いた不正取得は利用規約違反に当たり、アカウント停止や法的リスクにつながる可能性があります。
公式に提供されているデータや、正規の外部ツールを利用するのが基本姿勢です。
また、プライバシーや個人情報の取り扱いにも配慮が求められます。
特定のユーザー個人を過度に分析したり、データをそのまま公開したりすると、プライバシー侵害やコンプライアンス違反になりかねません。
特に企業が分析を行う場合は、利用目的を明確にし、適切な範囲で活用することが大切です。
さらに、数値データだけに依存しないことも重要です。
フォロワー数やエンゲージメント率は参考になりますが、それだけで評価するのでなく、投稿内容の文脈やフォロワーとの関係性も読み取る視点が欠かせません。
数字と内容を組み合わせて分析すれば、より実践的で信頼性の高い示唆を得られるでしょう。
他人アカウント分析を成果に生かす方法
分析はただ行うだけでなく、自社の成果に結び付けることが重要です。まず競合アカウントとの比較から自社運用の改善点を探れます。
投稿頻度や時間帯、エンゲージメント率を比較すれば、自社の運用に不足している要素が明らかになるでしょう。
次にフォロワーが伸びやすい投稿の特徴を参考にしましょう。
例えば画像や動画を効果的に使った投稿が伸びやすい場合、自社でもビジュアルを強化する戦略を検討できます。
またインフォグラフィックや事例紹介など、ユーザーにとって有益な情報が支持されている傾向が見えれば、自社コンテンツに取り入れる価値があります。
さらには、投稿のタイミングやハッシュタグ戦略も活用のポイントです。
他社が特定の曜日や時間帯に投稿して成果を上げている場合、そのパターンを参考にテストを行うと、改善が期待できます。
ハッシュタグも同様で、関連性の高いタグをうまく組み合わせるとより広い層にリーチ可能です。
このように分析結果を単なる数値の確認で終わらせず、施策に反映することが成果につながります。
他人アカウントの事例から学び、運用改善のサイクルに組み込むのが効果的です。
まとめ
他人アカウント分析は、SNSマーケティングを成功に導く有効な手段です。自分のアカウントだけでは得られない競合やインフルエンサーの動向を把握することで、市場の流れを理解しやすくなります。
公式アナリティクスでは自分のアカウントしか分析できないため、外部ツールを活用して情報を補完する必要があります。
投稿傾向やフォロワー層を比較すれば、自社の改善点や新しい戦略を導き出せるでしょう。
他人アカウント分析はマーケティング施策やインフルエンサー戦略とも直結するので、積極的に取り入れるべき取り組みといえます。
Quid Monitorでは、トレンド分析を通じて人気の高い他人の投稿を把握できる他、競合比較やフォロワー推移の可視化といった多角的なデータ分析が可能です。
自社の施策改善や競合調査を効率的に進めたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
Quid Monitor(旧NetBase)の詳細・資料ダウンロードはこちら







